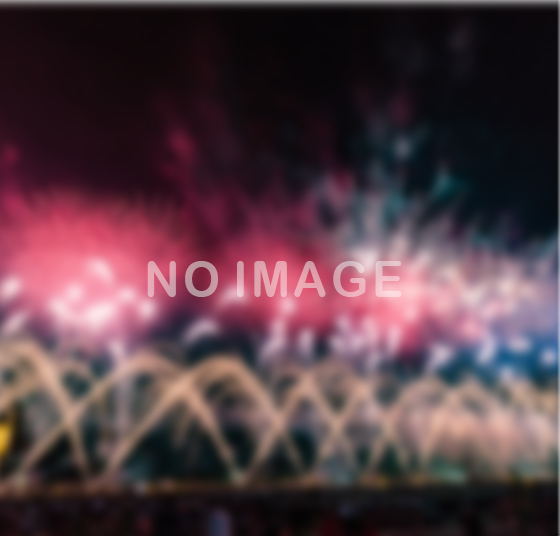新型コロナウイルスの影響により、全国各地のお祭りや花火大会の多くが中止・延期される中、国の緊急事態宣言が解除されたことを受け、今後のイベントの開催可否について改めて検討する主催者や自治体が増えてきています。
オンラインとリアルを織り交ぜながらの祭りの開催、ドライブインでの鑑賞といった人混みを避ける方法で開催を決定した花火大会など、新たなカタチでのお祭りが産み出され始めました。
この記事では、「お祭りで元気になりたい」と思っているみなさんに、さまざまな工夫をしながら開催を予定しているお祭りをご紹介します。
※2022年10月28日現在の情報です。開催情報は変更となる場合があります。
◎最新情報
【静岡県】熱海海上花火大会

■開催日(2022年秋~冬):10/15(土)・11/5(土)・11/20(日)・12/4(日)・12/18(日)・12/24(土)
■時間:午後8時20分~午後8時40分
■場所:熱海湾(熱海サンビーチ~熱海港)※2022年は有料観覧席を設置しません
■詳細:あたみニュース公式サイト
熱海海上花火大会は静岡県熱海市で開催される花火大会で、年間で10回以上開催されるいわば熱海の名物的なイベントです。会場の熱海湾は、山に囲まれた「すり鉢」状の地形のため、花火の音が反響する音響効果があり、花火業者さんも絶賛するそうです。オマツリジャパンでは、これまでに熱海海上花火大会の魅力や、コロナ禍で一時休止から再開した大会の様子などを詳しくレポートしてきました。ぜひこちらもあわせてご覧ください!
【兵庫県】赤穂義士祭
 https://omatsurijapan.com/blog/ako-gishisai-2/
https://omatsurijapan.com/blog/ako-gishisai-2/
■開催日時:12月14日(水曜日)10時~16時頃
パレード:11時30分~15時頃
露店販売:10時~16時
忠臣蔵交流物産市:10時~16時頃
■場所:赤穂城跡、お城通り、いきつぎ広場周辺
■詳細:赤穂市ホームページ
赤穂義士祭は、元禄年間に赤穂の義士が本懐を遂げた12月14日に毎年、赤穂市で開催されています。前半には祭気分を盛り上げるサークルによるパレードが行われます。後半は「忠臣蔵」の世界が市内に溢れます。赤穂義士祭については、過去の現地からの詳細なレポートを掲載しております!ぜひご覧ください!
【愛知県】花祭
 https://omatsurijapan.com/blog/hanamatsuri-succession/
https://omatsurijapan.com/blog/hanamatsuri-succession/
■開催日:11月~1月
※各地区によって日程が異なります。詳しくはこちらをご確認ください
■開催場所:愛知県北設楽郡東栄町 11地区
※地区によって、非公開の地区もあります。詳しくはこちらをご確認ください
■詳細:東栄町ホームページ
「花祭」は、国の重要無形民俗文化財に指定されている伝統のお祭り。町内の11カ所の地区(布川地区は休止中)で、11月上旬から1月中旬にかけ、開催されます(本年度の開催は非公開となる地域もあります)。一昼夜をかけて30〜40種類の儀式や舞が行われるという、集落を挙げての盛大なお祭りです。過去にインタビューした記事を掲載しているのでぜひご覧ください!